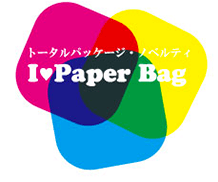最近は「脱プラスチック」や「サステナブル」といった言葉をよく耳にするようになり、紙コップの存在も改めて注目されています。
紙コップは日常生活に欠かせない便利なアイテムですが、実はその素材や捨て方によって環境への影響は大きく変わるのです。
そこでこの記事では、紙コップとSDGs(持続可能な開発目標)の関係をわかりやすく整理し、エコ素材の種類や企業の取り組み、そして私たち消費者ができることを徹底的に解説します。
SSDGsと紙コップの関係

まず押さえておきたいのが、紙コップがSDGsのどの目標に関連しているかという点です。
目標12「つくる責任 つかう責任」
紙コップを必要以上に消費しないこと、再利用やリサイクルを推進することは、この目標に直結します。
目標13「気候変動対策」
プラスチック削減やCO2排出低減に寄与する紙コップ素材の選択は、温暖化防止とリンクします。
目標14「海の豊かさを守ろう」・目標15「陸の豊かさも守ろう」
森林資源や海洋汚染に配慮した紙コップは、自然環境全体を守る取り組みに繋がります。
つまり紙コップは「使い捨て」の象徴である一方で、脱プラ社会や循環型社会を進める象徴的な製品でもあるのです。
なぜエコな紙コップが必要なのか
世界的にはプラスチック削減の流れが加速し、ストローやレジ袋の規制が広がっています。
日本でもレジ袋の有料化が契機となり「日常的に使う資材をどう選ぶか」への関心が高まりました。
紙コップは一見「紙だからエコ」と思われがちですが、実際は内側に樹脂コーティングがされているためリサイクルが難しいケースが多いのです。
だからこそ、本当のエコを考えたときには、素材や廃棄方法に配慮した「エコ紙コップ」を選ぶことが重要になっています。
3Rと紙コップ

SDGsや環境配慮の基本は 3R(リデュース・リユース・リサイクル)です。
紙コップの場合は次のように考えられます。
Reduce(削減)
必要以上に使わないことが大前提。
保温性のための二重構造カップも、必要なとき以外は避けるのが望ましいでしょう。
Reuse(再利用)
飲料用としての再利用は衛生面から推奨されません。
ただし、DIYや植木鉢カバー、小物入れとしての二次利用は可能です。
Recycle(再資源化)
従来の紙コップは樹脂コーティングがネックでしたが、水性バリア紙や専用回収ルートの整備でリサイクルの動きが進んでいます。
エコな紙コップの種類と特徴

環境配慮型の紙コップにはいくつかの種類があります。
当メディアを運営しているI Love Cupでも、環境に配慮した紙コップをご用意しております。
以下にそれぞれの特徴をご紹介いたします。
①バガス(サトウキビ繊維)
サトウキビを搾った後に残る繊維を活用した素材。
非木材資源を利用することで森林伐採を抑えられ、廃棄物削減にもつながります。
②FSC認証紙
森林資源が持続的に管理されていることを証明するFSC認証を受けた紙。
「環境に配慮した商品を選んだ」という消費者の安心感にも直結します。
③生分解性樹脂(PLAコーティング)
トウモロコシなど植物由来の素材を使ったコーティング。
堆肥化施設では分解可能で、プラスチック依存を減らせます。
ただし一般ごみの中では分解しにくい点が課題です。
④水性バリア紙
PEやPLAを使わず、水性コーティングで耐水性を持たせた紙。
リサイクル性が高く、分別回収が容易という利点があります。
環境負荷の低い選び方・使い方

紙コップを選ぶ際には以下のポイントを意識しましょう。
単層 vs 二重構造
単層紙コップはもっとも一般的で、資材使用量が少なくコストや環境負荷を抑えやすいのが特徴です。常温の飲み物や短時間の利用に向いており、イベントやオフィスなど大量使用のシーンに適しています。
一方、二重構造紙コップ(二重壁カップ)は、外側にもう一層を重ねることで保温性・断熱性を高めています。
熱い飲み物を入れても持ちやすく、スリーブが不要になるメリットがありますが、その分資材使用量が増え、コストや廃棄物量も多くなるのがデメリットです。
エコの観点からは「常に二重構造を選ぶ」のではなく、用途に応じて単層と二重を使い分けることが重要です。
たとえばオフィスの給湯室でのお茶や水なら単層、カフェで提供されるテイクアウトのホットコーヒーなら二重構造、といった使い分けが持続可能な選択につながります。
過剰包装の回避
フタやスリーブは本当に必要かを見直しましょう。
不要な付属品を避けるだけでも資源削減につながります。
実際に、海外の一部の大学カフェ(オハイオ州立大学の学内カフェ)では「希望者のみリユーザブルスリーブを提供」する仕組みに変えて、紙スリーブの無駄を減らす取り組みも進められています。
こうした具体的な対策が、過剰包装削減の身近なモデルになり得ます。
コンポスタブル表示への配慮
紙コップの中には「コンポスタブル(堆肥化可能)」と表示されたものがあります。
これは本来、産業用コンポスト施設で処理した場合に分解されるという意味です。
ただし、日本では対応施設が限られており、多くの自治体では一般可燃ごみ扱いになります。
そのため、「家庭で自然に分解する」という誤解に注意し、必ず自治体ルールに従って廃棄しましょう。
紙コップ廃棄とリサイクルの課題

多くの紙コップは「紙+樹脂コート」のため、一般的な紙リサイクルには混ぜられません。
そのため現状では「燃えるゴミ」として廃棄されるケースが大半です。
一方で、近年は「水性バリア紙」や「PLA」などリサイクルしやすい素材、さらにスターバックスのように専用回収スキームを持つ企業が登場し、改善が進みつつあります。
海外の動向
EUの取り組み
使い捨てプラスチック規制が厳格化し、紙カップや代替素材が急速に普及。
リユーザブルカップの導入も進んでいます。
北米の取り組み
マクドナルドなど大手外食チェーンがPLAやバガス容器を導入。
店舗規模でのエコ素材利用が加速しています。
英国の取り組み
スターバックスやコスタが紙コップ回収プログラムを拡大。
リサイクルルートを整備する動きが先行しています。
海外のこうした事例は、日本の取り組みにも大きな影響を与えています。
SDGsに配慮した企業・事例紹介
スターバックス

FSC認証紙カップの導入
2020年11月以降、日本全国の店舗で提供される紙カップはすべてFSC®認証紙を使用。
森林保全に配慮した素材が全面的に導入されています。
カップリサイクルの実証実験
2021年から東京都・丸の内エリアなど一部地域で、使用済みカップを回収・再資源化するプログラムを開始。
実証店舗を増やしながら、循環型社会に向けた仕組みづくりを進めています。
リユーザブルカップ割引制度
タンブラーやマグカップを持参すると、ドリンク代から22円割引される制度を全国で導入。
持続可能な行動を促す代表的な仕組みになっています。
ロフト

「ロフト グリーンプロジェクト」
環境配慮型商品を広げるための取り組みで、FSC認証紙や紙パウチを活用したアイテムを展開。
店舗ごとにサステナブル特集を行い、消費者に環境配慮を意識づけています。
サステナブル商品の拡大
リサイクル素材やアップサイクル製品を扱い、文房具や雑貨のジャンルでもエコ素材を積極的に採用。
生活の中で気軽に取り入れられるサステナブルな商品を提供しています。
店頭回収プログラム
化粧品容器などの店頭回収を行い、再資源化ルートを整備。
資源循環に直接貢献する仕組みを整えています。
コンビニ・外食チェーン
セブン&アイ(紙容器リサイクル実証)

セブン&アイは日本テトラパックと連携し、イトーヨーカドーの一部店舗で紙容器を回収する「楽☆リサ」ボックスを設置しました。
利用者は使用済み紙容器(紙パックなど)を投入すると、スマホアプリでポイントが貯まる仕組みで、楽しくリサイクルに参加できます。
この取り組みは、将来的に紙コップや紙製品のリサイクル拡大にもつながると期待されています。
マクドナルド
マクドナルドでは世界的にプラスチック削減を進めており、日本でも紙コップを含む「使い捨て容器のあり方」を見直す流れを段階的に行なっており、紙やバイオ素材への切り替えが順次進んでいます。
2022年
神奈川・京都の店舗から、紙ストローと木製カトラリーを導入。
その後、全国展開を進めています。
2023年
サイドサラダの容器を紙製に変更。
2024年11月
コールドドリンクのカップとフタをバイオマスプラスチックやリサイクルPETへ移行。
2024年12月
マックフルーリーの容器からフタを廃止し、スプーンも木製に変更。
すべてFSC認証素材を使用。
さらにマクドナルドは2025年末までに、すべての容器や包装を再生可能・リサイクル素材に切り替える方針を掲げています。
消費者ができるアクション
・必要なときだけ紙コップを使う
・普段はマイボトルやリユーザブルカップを持参
・FSC認証紙やバガス、PLAコーティングなどのエコ素材を選ぶ
・廃棄は必ず自治体のルールに従い、リサイクル可能な場合は資源に分別
こういった小さな行動の積み重ねが、持続可能な社会の推進力になります。
まとめ
紙コップは選び方や使い方次第で、環境への影響が大きく変わります。
バガスやFSC認証紙などエコ素材の普及、企業や自治体の取り組みが進む今、私たち一人ひとりが賢く選ぶことがSDGsへの貢献につながります。

 Menu
Menu
 シングル紙コップ
シングル紙コップ 断熱系紙コップ
断熱系紙コップ クリアカップ
クリアカップ バイオマス系カップ
バイオマス系カップ ジェラート
ジェラート スリーブ
スリーブ ワンポイント印刷
ワンポイント印刷 ポップコーンカップ
ポップコーンカップ インモールドカップ
インモールドカップ その他アイテム
その他アイテム