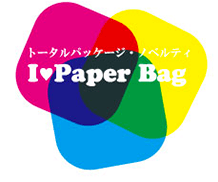テイクアウトやイベント、オフィスでのドリンク提供など、さまざまな場面で使われる紙コップとプラカップ。
見た目や使い勝手は似ていますが、「コスト」「耐熱性」「環境対応」「ブランディング」などの面で大きな違いがあります。
たとえば、冷たいドリンクにはプラカップが適していても、ホットドリンクに使えば変形のリスクが。
一方で紙コップも、内面コーティングや素材選び次第でコストや環境への影響が大きく変わってきます。
「安いから」
「よく見かけるから」
などと行った理由でなんとなく選んでしまうと、結果的に無駄な出費やお客様からの評価低下につながる可能性もあるためご注意ください。
そこでこの記事では、紙コップとプラカップの違いを多角的に比較しながら、用途別の最適な選び方、そして最新のトレンド素材まで詳しく解説いたします。
飲食店・イベント運営者・企業の購買担当者はもちろん、SDGsやエコに関心のある方にも役立つ内容になっています。適切な選定でコスト削減とブランド価値の向上を目指しましょう。
紙コップとプラカップの特徴と用途まとめ

紙コップとは?特徴・使われるシーン
紙コップは、内側にポリエチレンなどの耐水加工を施した紙製のカップです。
主にホットドリンク(コーヒー、紅茶)に適しており、断熱性や手触りの柔らかさが特徴です。
飲食店のテイクアウト用や自動販売機、イベント会場、病院・福祉施設など幅広い場所で使われています。
プラカップとは?特徴・使われるシーン
プラカップ(プラスチックカップ)は、主にPET(ポリエチレンテレフタレート)やPP(ポリプロピレン)で作られた透明なカップです。
アイスコーヒーやジュース、ビールなどの冷たい飲料に向いており、透明性の高さから見た目の清涼感やブランド演出にも効果的です。
カフェや屋台、フェスなどで多く使われます。
紙コップとプラカップの違いを比較

価格・コストの違い
一般的にプラカップの方が単価は安い傾向があります。
ただし、耐熱性のある特殊素材を使う場合はコストが上がります。
紙コップは素材コストが高く、加えて耐熱用の二重構造や断熱スリーブを使う場合はさらにコストアップします。
使用シーンと必要な機能に応じて、適切なコストバランスを考える必要があります。
耐熱性・耐冷性の違い
紙コップは耐熱性に優れ、ホットドリンクに最適です。
一方でプラカップは基本的に耐熱性が低く、高温の飲料を入れると変形や劣化の原因になります。
ただし、プラ素材でもPP(ポリプロピレン)は比較的耐熱性があり、一部ホット用にも対応可能です。
耐冷性については、どちらも問題ありませんが、冷たいドリンクで紙コップを使うと結露が出やすく、強度が落ちる場合もあるため、プラカップの方が安定性があります。
環境対応・リサイクル性の違い
環境対応の観点では、紙コップは「紙」という印象からエコに見られがちですが、実際には内側にポリエチレンコーティングがあるためリサイクルは難しく、焼却処理が基本です。
一方、PET製プラカップは自治体によってはリサイクル対象として回収されるケースもあります。
ただし、近年ではバイオマスインキ使用やFSC認証紙を使った紙コップ、再生PETを使ったプラカップなど、環境対応を意識した製品も増えてきています。
SDGs対応を意識するなら、素材の選定段階から注意が必要です。
ブランディング・印刷対応の違い
印刷の自由度は、紙コップの方が高く、フルカラーでロゴやメッセージを載せやすいです。
紙という素材の特性上、マットな風合いが出やすく、ブランドの世界観を伝えやすいのもメリット。
一方、プラカップも印刷可能ですが、単色印刷が主で、細かいデザインや多色刷りは制限があります。
透明性を活かした中身+ロゴの組み合わせも、演出として有効です。
どちらを選ぶべき?シーン別おすすめ

飲食店・カフェ・テイクアウトで使う場合
ホットドリンクを提供するなら紙コップが基本。
特にテイクアウト需要が多い店舗では、手に持った際の快適さや安全性が重要です。
アイスドリンク中心の場合はプラカップが向いています。
フタやストローとの組み合わせも考慮しましょう。
イベント・オフィス・ホテルで使う場合
コストや回収のしやすさを考えると、冷たい飲料にはプラカップが有利。
使い捨ての清潔感と軽さもポイントです。
ただし、ホテルのルームサービスやビジネス会議では、印象を重視して紙カップが選ばれることもあります。
SDGs・サステナブルな観点で選ぶなら
近年はSDGsや環境配慮の観点から、容器の素材選びそのものが企業や店舗の姿勢として問われるようになっています。
紙コップでは、FSC認証紙を使った製品や、植物由来のバイオマスインキで印刷されたタイプが特に注目されています。
さらに、内面の防水加工に使う樹脂もバイオマス化するなど、紙素材の環境性能は進化を続けています。
一方、プラカップについては「使い捨て」から「繰り返し使う」方向にシフトする動きも見られます。
再生PET(リサイクルプラスチック)を使った製品や、洗って再利用できるリユースカップが、フェスや企業イベント、エコ意識の高い飲食チェーンなどで採用されています。
どちらの素材を選ぶにしても、使い捨て前提の考え方から脱却し、製造〜廃棄までの環境負荷をトータルで捉える視点が求められています。
消費者からの信頼を得るためにも、SDGsの観点から納得感のある選択を心がけましょう。
紙コップ・プラカップの選び方のポイント

間違えやすいポイントとよくある失敗例
紙コップやプラカップは一見シンプルな使い捨て容器に見えますが、適切に選ばなければ業務に支障をきたすケースもあります。
以下は実際によくある失敗例です。
・ホットドリンクをプラカップに注いでしまい、熱で変形や液漏れが発生した
・アイスドリンクを紙コップで提供した結果、結露によってテーブルが濡れたり、手が濡れて不快になった
・ブランドロゴを大きく見せたいのに、プラカップの素材特性により印刷の発色が弱く、意図したデザインを再現できなかった
こうしたトラブルは、用途に対する素材特性の理解不足や、発注前の確認不足から起こりがちです。
導入時には実際の提供シーンをシミュレーションし、温度、見た目、持ちやすさまで考慮した上で選ぶことが重要です。
仕入れ時に確認すべき仕様・条件
容器選びで失敗しないためには、発注前に以下のポイントをしっかり確認することが欠かせません。
・耐熱性・耐冷性など、使用温度の範囲(例:80℃対応など)
・容量(ml)とサイズ展開(高さ・直径)
・フタ・ストロー・スリーブなど、周辺資材との互換性があるかどうか
・納品までのリードタイムと、在庫対応の柔軟性(定期発注が可能か)
・最低ロット数と、初回発注時に無料または有料でサンプル提供が可能かどうか
特にサンプル提供の有無は、現物確認をした上で仕入れ判断ができるかどうかに直結します。
見た目だけでなく、手触りや強度なども確認しておくことで、トラブルを未然に防ぐことができます。
また、初回注文時には印刷品質もチェックしておくと安心です。
ブランドの印象に直結するため、細部までこだわりたい方は、カスタマイズ対応力がある仕入先を選ぶようにしましょう。
今後の動きとトレンド素材

脱プラ対応素材・新技術
環境負荷を減らす目的で、PLA(ポリ乳酸)など植物由来のバイオプラスチックや、水性ラミネート技術などが注目されています。
これにより従来のプラスチック使用量を抑えた商品が続々と登場しており、当メディアを運営する、I Love Cupでもさまざまなエコロジー素材のカップを取り扱っております。
紙カップの進化(バリア性・紙+樹脂複合など)
紙コップは今後、バリア性を高めた素材や、水に強い紙素材との複合など、より機能性を高めた製品へと進化しています。
アルミ蒸着や耐水紙など、食品用途に特化した設計も進んでおり、リサイクル性と性能の両立が求められています。
まとめ
紙コップとプラカップには、それぞれ異なる特性があります。
ホットとアイス、ブランドイメージ、環境配慮など、何を重視するかによって最適な選択肢は変わります。
仕入れ先を選ぶ際は、希望に合った素材や仕様に柔軟に対応できるパートナーを選ぶことが重要です。
紙カップやプラカップを小ロットで導入したい場合は、I Love Cupなど、豊富なラインナップと短納期に対応している専門店の利用がおすすめです。
用途やコンセプトに合ったカップ選びで、より良い提供体験とブランド価値の向上を目指しましょう。

 Menu
Menu
 シングル紙コップ
シングル紙コップ 断熱系紙コップ
断熱系紙コップ クリアカップ
クリアカップ バイオマス系カップ
バイオマス系カップ ジェラート
ジェラート スリーブ
スリーブ ワンポイント印刷
ワンポイント印刷 ポップコーンカップ
ポップコーンカップ インモールドカップ
インモールドカップ その他アイテム
その他アイテム